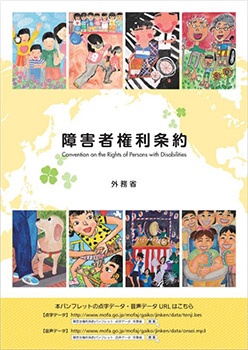左の「女性」は今年1月市民への手続き支援や書類発行のアシスタントに採用され、目覚ましい業績を上げ、今年9月にはなんとこの国の首相から「大臣」として任命されました。担当部署は公共入札の監督・評価など政府と民間業者の入札手続きや契約決定などの公共調達に関するものです。公共事業につきものの賄賂や汚職の削減、透明性の確保、人為的なバイアスや圧力・利益相反などを減らすことを目的としているそうです。彼女に任せれば「えこひいき」も「人間のしがらみ」もない!!
「彼女」の名前はディエラと言います。ディエラ(Diella)は世界初のAI(人工知能)による仮想閣僚です。そして、その国はアルバニア。ディエラはいかなる圧力も感じない。なぜなら実体がなくただサイバー空間に存在する「もの」だから。左の写真は彼女のアバターです。もう少しAIらしいテクノポップな姿かと思ったら、民族衣装をまとったなんとも普通のおばさんアバターでした。
もちろん、この試みに否定的な人も多くいるようですし、これからも多くの難問が待ち構えていると思う。しかし、この試みの多くの失敗と成功が共有財産となり人類の叡智に結びつくかもしれない。スポーツのビデオ判定以上の「価値」を生み出し、多くの人に信頼され、光り輝く未来社会の行政の在り方の道標になれば…と思う。 そういえば、ディエラ(Diella)とは「太陽」を意味する名前だそうです。
「AIが大臣に」ああ、もうこんな時代になってきたのかと、ぼんやりと未来社会の夢を追いかけていたら、テレビでは相変わらず力による正義を振りかざす指導者たちが世界を振り回している。まるで弱肉強食の帝国主義時代に戻ってきたようだ。 私は、戦争の実相を見れば誰もが反戦の思いを持つと思っていた。けれど、ウクライナ戦争の初期では、現に爆撃を受けている普通の家族がシェルターの中からスマホで情報発信し、それをリアルタイムで世界中の人が見ているという人類初の状況にあったにもかかわらず、そして、ガザでは毎日のように行われる爆撃と病院に運ばれる子ども達の映像を見ているというのに・・・。まだ世界は動かない。(…私も動かない。)「”これではいけない!”マグマ」がきっと近いうちに爆発すると思いたい。



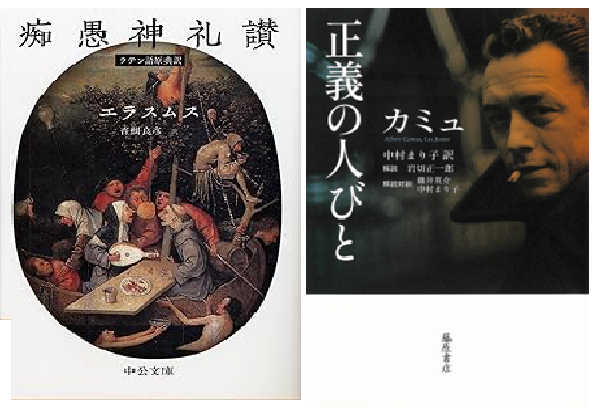 今年も、8月6日、9日、そして15日がやってきます。8月という月は、否応なく戦争の記憶や平和への思いに心を向けさせられる時期です。甲子園では、かつて正午に試合を中断して黙とうを捧げていましたが、今年はどうなのでしょうか。酷暑の影響で、日中の試合そのものがなくなるとも聞きます。
今年も、8月6日、9日、そして15日がやってきます。8月という月は、否応なく戦争の記憶や平和への思いに心を向けさせられる時期です。甲子園では、かつて正午に試合を中断して黙とうを捧げていましたが、今年はどうなのでしょうか。酷暑の影響で、日中の試合そのものがなくなるとも聞きます。 2025年6月29日評価員研修会風景
2025年6月29日評価員研修会風景